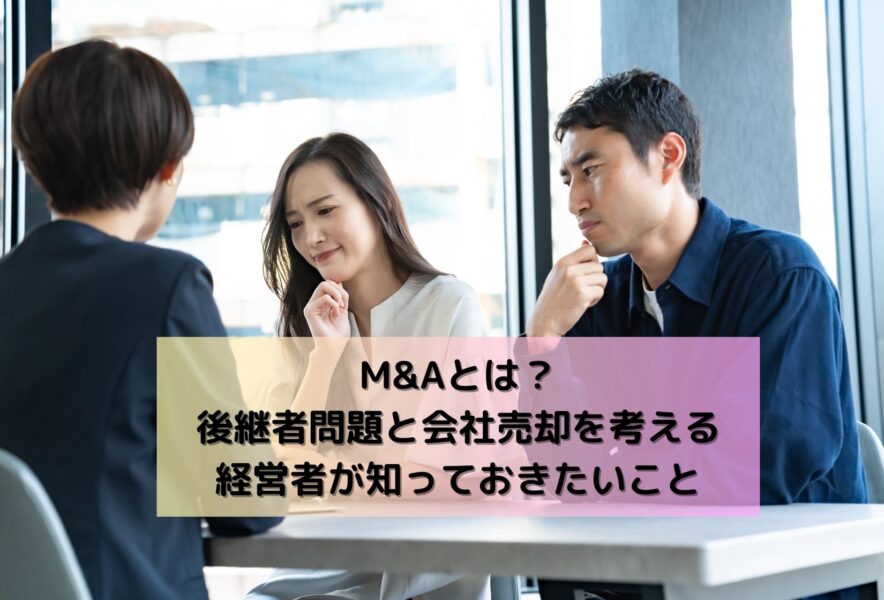会社の将来や事業継承に悩む経営者・オーナー社長にとって、「M&A」は選択肢の一つとして大きく注目されています。近年では後継者不足や市場のグローバル化などを背景に、事業承継を目的としたM&Aが増加しているのが現状です。そこで本記事では、「M&Aとは何か?」という基本から、会社売却を検討する際に知っておくべきメリット・注意点・進め方などを詳しく解説します。自社に合った最善の選択をするために、ぜひ最後までお読みください。
M&Aとは
M&Aとは、Mergers(合併)とAcquisitions(買収)の頭文字をとった用語で、企業同士が一つの組織として統合したり、一方が他方を買収することを指します。一般的には「企業の吸収・合併や買収」を総称してM&Aと呼び、事業規模の拡大や新規事業領域への参入、後継者問題の解決などを目的として実施されます。
M&Aの定義と概要
M&Aは大きく分けると合併(Mergers)と買収(Acquisitions)の2つの形態があります。合併とは、複数の企業が統合して一つの企業になることを指し、買収は株式や事業を取得することで経営権を手に入れることを意味します。
M&Aの特徴としては、経営権の移転や組織の統合が伴うため、単なる資本提携や業務提携とは異なる点が挙げられます。シナジー(相乗効果)を期待して行われるケースが多く、新製品の開発や販路拡大、人材の確保といったメリットが得られることが魅力となっています。
M&Aが注目される背景
近年、M&Aが注目されている背景には、グローバル化や国内市場の成熟化に伴う競争激化が挙げられます。大企業だけでなく、中小企業でも新たな成長戦略としてM&Aを積極的に活用する動きが見られるようになっています。
また、日本の中小企業は後継者不足に悩むケースが多いという現状も、M&Aが注目される一因です。事業を継ぐ人材が見つからず、廃業や倒産を回避するための手段としてM&Aを選択する経営者が増えています。さらに、国や地方自治体も事業承継に積極的に取り組むようになり、M&A支援に力を入れていることも後押しとなっています。
中小企業におけるM&Aの現状
中小企業のM&A件数は、経営者の高齢化や人手不足、地域経済の衰退といった課題を背景に、増加傾向にあります。特に日本では、経営者の多くが60代以上となり、事業承継のタイミングを迎えている企業が少なくありません。
一方で、中小企業がM&Aを行う際には、適切な情報収集や専門家のサポートが欠かせません。大企業に比べて経営リソースが限られている中小企業こそ、早い段階で事業承継を見据えた準備を行うことで、企業価値を損ねることなくM&Aを実現できます。近年は、事業承継に特化したM&A仲介会社や金融機関のサポートも充実してきており、正しい知識とサポートを得ることでスムーズなM&Aが可能となっています。
会社売却を検討する理由とタイミング
企業を経営していると、様々な局面で「このタイミングで売却すべきかどうか」と悩むことがあります。特に後継者問題や経営者の高齢化、事業の将来性への不安など、経営環境の変化やライフプランの変化によって、会社売却を検討するのは決して珍しいことではありません。以下では、オーナー社長が会社売却を検討する主な理由と、そのベストなタイミングを見極めるためのポイントをご紹介します。
経営者が会社売却を検討する主な理由
1. 後継者不足
子供や親族、社内の幹部候補などに事業を継がせる人材がいない場合、会社を廃業するよりも第三者に売却して存続させることが選択肢として浮上します。後継者不足は日本の中小企業において深刻な問題となっており、M&Aによって事業承継を図るケースが増えています。
2. 経営リスクや負担の軽減
経営者個人が抱える債務保証などのリスクや、日々の経営判断に伴う重圧から解放されることは、大きなメリットの一つです。特に長年経営してきた経営者にとって、「責任のある立場」から退き、第二の人生を歩みたいという願望は自然な流れといえます。
3. 企業価値の最大化・資金化
会社を売却することで、これまで築いてきた企業価値を資金として手にすることが可能です。引退資金や新たな事業への投資など、経営者にとっては次のステージへ進むための大きな原資となります。
4. 戦略的撤退・事業再編
主力以外の事業を売却して経営資源を集中させる、あるいは市場環境の変化で成長が見込めない事業から撤退するなど、事業再編の一環としての売却を選ぶケースもあります。利益が出ているうちに売却することで、リスクを最小限に抑えることができます。
適切なタイミングを見極めるポイント
1. 業績が安定または好調な時期
会社の価値は業績に大きく左右されます。企業として収益が安定している時期や業績が好調な時こそ、買い手からの評価も高まり、売却価格の交渉が有利になる傾向があります。反対に、赤字や業績不振が続いてからでは売却条件が悪化する可能性があります。
2. 後継者不在の早期把握
後継者がいないことが明確になった時点で、「いつかは売却を検討しなければならない」と考える経営者は少なくありません。時間をかけて準備するほど良い条件で売却がしやすくなるため、早めのタイミングで一度M&A専門家に相談することが望ましいです。
3. 業界の動向や市場環境
買い手企業が積極的にM&Aを行っている業界や、拡大路線をとっている時期など、市場全体の動きも大切な指標になります。競合他社が同業種のM&Aを活発化させているタイミングは、相乗効果を期待できる案件として注目されることも多いのです。
4. 自身のライフプランとの整合性
経営者個人の健康状態や家族状況、セカンドライフの構想なども考慮に入れた上で、ベストな時期を判断することが重要です。会社の状況だけでなく、経営者自身の人生設計とマッチしたタイミングで検討すれば、売却後の後悔も少なく済むでしょう。
“売り時”を逃さないための注意点
1. 早期の情報収集と準備
M&Aは時間と手間がかかるプロセスです。候補先を探し、デューデリジェンス(買収監査)や価格交渉を経てクロージングに至るまで、短くても数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。「いつでも売りに出せる」という意識で経営状況や財務諸表を整備しておくとスムーズです。
2. 本業に悪影響を及ぼさない
売り時を逃す要因の一つとして、M&A活動に時間をかけすぎて本業が疎かになることがあります。買い手は業績や今後の成長性をシビアに評価するため、実務を上手に分担しながら、業績を落とさないように留意する必要があります。
3. アドバイザー選びは慎重に
M&A仲介会社や専門家の選定を誤ると、売却活動が長引いたり、不利な条件で売却せざるを得なくなることもあります。実績や得意分野、担当者との相性などを総合的に判断し、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。
4. 長期的視点で売却後を考える
「高値で売り抜ける」だけがM&Aのゴールではありません。売却後に社員や取引先、地域への影響をどう最小化・最適化するかを考えることも、経営者の責任といえます。将来的な社名やブランドの取り扱い、雇用継続など、長期的視点で納得のいく条件を探ることが重要です。
M&Aの種類
M&Aと一口に言っても、実際にはさまざまな手法があります。大きく分けると株式の移転によって経営権を取得する株式譲渡、事業資産のみを譲り受ける事業譲渡、企業を合併して一体化する合併・吸収などに分類されます。目的や状況によってどの手法を選択するかが変わってくるため、自社の特性や経営戦略に合った手段を見極めることが大切です。
株式譲渡
株式譲渡は、譲渡企業の発行済株式(または大部分)を買い手企業が取得することで、経営権を移転する手法です。株主構成を変えるだけで会社の法人格や組織はそのまま存続するため、従業員の雇用契約や取引先との契約関係などを引き継ぎやすいという特徴があります。
また、手続きが比較的シンプルである一方、買い手企業にとっては譲渡企業が抱える債務やリスクも一括して引き継ぐことになるため、慎重にデューデリジェンス(企業調査)を行う必要があります。
事業譲渡
事業譲渡は、譲渡企業が保有する特定の事業や資産を買い手企業に移転する手法です。こちらは株式そのものではなく、必要な事業部門や設備、知的財産権などを個別の契約で譲渡することになります。
買い手企業としては不要な資産や負債を切り離して買収できるため、リスクを限定しながら事業拡大を図ることができます。ただし、従業員の雇用や取引先との契約を改めて結び直す必要があるなど、手続きが煩雑になりやすい点には注意が必要です。
合併・吸収(統合)
合併とは、複数の企業が一つの法人格として統合する手法です。特に一方の会社に他方が吸収される形を吸収合併、新たに設立する会社に統合する形を新設合併と呼びます。
合併のメリットとしては、組織や経営資源を一体化しやすい点が挙げられます。しかし、組織再編や統合後の企業文化の調整が必要になるなど、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)で課題が生じやすいという特徴もあります。
その他の形態(分割・業務提携など)
M&Aには上記の他にも、会社分割や株式交換、業務提携(資本提携を含む)など、多様なスキームがあります。会社分割は一部の事業を切り離して別法人に移すことで、事業再編の柔軟性を高める手法です。また、業務提携や資本提携は、完全に会社を買収・合併するのではなく、出資や共同事業によって協力関係を築く形となります。
自社のビジョンや経営方針に合う最適な手法を選ぶためには、それぞれの特徴やリスクを理解することが不可欠です。専門家やアドバイザーの助言を得ながら検討することで、最も効果的なM&Aスキームを実行できる可能性が高まります。
M&Aのメリット
M&Aは単なる企業売買だけでなく、経営戦略の一環としてさまざまなメリットをもたらします。売り手企業、買い手企業、さらには従業員や取引先といったステークホルダーに対しても、それぞれプラスに働く可能性があります。ただし、メリットを最大限享受するためには、適切なプロセスと事前準備が不可欠です。ここでは、M&Aがもたらす主なメリットを詳しく見ていきましょう。
経営者・オーナー側のメリット
1. 後継者不在の解消
中小企業の大きな課題である「後継者不足」を解消できるのが、M&Aの大きな魅力です。経営を任せる適切な人材が社内外で見つからない場合でも、第三者に事業を引き継ぐことで、企業の存続と発展が期待できます。
2. 個人保証や債務リスクの軽減
経営者が個人保証を抱えている場合、会社を売却することで保証や債務の負担が軽減されるケースがあります。また、借入金などのリスクから解放されることで、オーナーのライフプランを柔軟に描けるようになるメリットもあります。
3. 経営資源の最大化
自社だけではなかなか成長が見込めなかった領域も、M&Aをきっかけに買い手企業との相乗効果を発揮する可能性があります。また、創業者が培ってきたノウハウやブランドを、より大きなマーケットやネットワークで活かせるのも魅力です。
買い手企業側のメリット
1. 新規事業領域への参入
既存事業では補えないノウハウや新しい顧客層をM&Aによって獲得できるのは、買い手企業にとって大きな利点です。新規プロジェクトをゼロから立ち上げるよりも、スピーディーかつ効果的に事業領域を拡大できます。
2. シナジー効果の期待
技術力や販売チャネル、顧客基盤などの経営資源を統合することで、付加価値の高い商品・サービスを展開できます。さらに、コスト削減や生産性の向上といったシナジーが得られることで、収益力の強化にもつながります。
社員や取引先にとってのメリット
1. 雇用継続とキャリアチャンス
M&Aによって経営が安定化すれば、廃業のリスクが減り、社員の雇用を守りやすくなります。新たなオーナーのもとで、キャリアアップや報酬改善など、働く環境が向上する可能性もあります。
2. 取引先との関係維持
事業を存続させることで、取引先企業との関係も継続できます。買い手企業が持つネットワークや信用力を活かし、取引量の拡大や新たなビジネスチャンスが生まれることも期待できます。
3. 地域経済への貢献
中小企業が廃業を回避して存続することは、地域社会にとっても大きなメリットです。雇用の維持や地元産業の活性化など、地域経済へのプラスの影響を与えることができます。
M&Aは、売り手・買い手だけでなく多くのステークホルダーにメリットをもたらす可能性があります。しかし、実際の成否を分けるのは、最終的に「そのメリットを実現するための準備と戦略」がどれだけしっかりと行われているかにかかってきます。最良の結果を得るために、綿密な計画と適切な専門家のサポートを得ることが重要です。
M&Aの流れと手続き
M&Aを成功させるためには、綿密な準備と的確なプロセス管理が欠かせません。大まかな流れとしては、事前準備からクロージングまで、一連のステップを順に踏んでいくことになります。ここでは、代表的な手続きを段階ごとにご紹介します。
1. 事前準備と目標設定
M&Aを検討し始めたら、まずは自社の状況を整理し、「なぜM&Aを行うのか」といった目的や目標を明確にすることが重要です。後継者問題を解決したいのか、事業領域を拡大したいのかなど、自社がM&Aに求める意図を整理することで、今後の戦略立案がスムーズに進みます。
また、売り手企業の場合は財務諸表や経営資料を整備し、自社の強みや魅力を改めて洗い出す作業を行いましょう。買い手企業の場合は、投資予算や取得後のシナジーなどをしっかり見極める必要があります。
2. バリュエーション(企業価値評価)
企業を売却する際には、バリュエーション(企業価値評価)が欠かせません。これは、どの程度の価格で譲渡(または買収)するのかを客観的に算出するプロセスです。バリュエーションの手法には、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法や類似会社比較など、複数のアプローチがあります。
必ずしも一つの手法だけで評価するわけではなく、複数の手法を組み合わせて相場や将来性を考慮しながら最終的な価格の目安を探るのが一般的です。売り手企業は、自社の企業価値を最大化できるよう、事前に収益性や成長性を高める努力が求められます。
3. ノンネームシートの作成・買い手候補探し
売り手企業が仲介会社やアドバイザーとともに、ノンネームシート(匿名情報による企業概要)を作成するのが次のステップです。ノンネームシートには、社名を伏せた上で経営内容や業績、強みなどを要約して記載します。これをもとに買い手候補へ提案を行い、興味を持ってくれた企業とマッチングを図るのです。
一方、買い手企業側では、希望条件に合う売り手企業が見つかれば、トップ面談やNDA(秘密保持契約)を結んで、より具体的な交渉段階へ移ります。
4. デューデリジェンスの実施
買い手企業が本格的に買収を検討する段階になると、デューデリジェンス(DD)を行います。これは、売り手企業の財務・税務・法務・人事・ビジネス面などを詳しく調査し、リスクや問題点がないかを確認する作業です。
売り手企業側としては、DDの結果を踏まえて買収条件や譲渡価格が変更される可能性があるため、正確な情報開示と誠実な対応が必要となります。ここで信頼関係が損なわれると、交渉が破談になるケースもあるので注意が必要です。
5. 最終契約とクロージング
デューデリジェンスが完了し、価格や条件に両社が合意すれば、最終契約を締結します。具体的には、株式譲渡契約や事業譲渡契約といった形で、譲渡対象や金額、支払い条件、契約違反時の対応などを明記した契約書を交わします。
その後、クロージング(実行手続き)をもって、正式に経営権が移転します。クロージング後も、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)と呼ばれる企業統合プロセスが円滑に進むよう、両社が協力して組織の再構築や社員への周知を行うことが肝要です。
以上が、M&Aにおける基本的な流れと手続きです。実際には企業規模や業界特性、買収スキームによってステップが変わることもありますが、いずれのケースでも事前準備と情報開示がポイントとなります。スムーズかつ納得のいくM&Aを実現するためにも、早い段階で専門家のサポートを受けながら慎重に進めましょう。
M&Aを成功させるためのポイント
M&Aは、企業同士の統合という大きな変革を伴うため、事前の準備やプロセス管理が不十分だと、思わぬリスクやトラブルを招くこともあります。一方で、しっかりと計画を立て、必要なステップを踏んでいけば企業価値の最大化や事業承継のスムーズ化を図ることが可能です。ここでは、M&Aを成功させるために押さえておきたい主なポイントをご紹介します。
戦略的な準備と事業計画の明確化
M&Aを検討する際は、まず経営ビジョンや事業目標を明確にし、「なぜM&Aを行うのか」という目的を再確認することが重要です。特に売り手企業の場合、後継者問題の解決が最大の目的なのか、それとも企業価値の最大化を狙うのかによって、具体的な売却プランが変わります。買い手企業においても、どの領域で強化を図るのか、取得後にどう成長戦略を描くかなどを、事前に綿密に検討しましょう。
適切なアドバイザー選び
M&Aは法務・財務・税務など、専門的な知識が求められるため、信頼できるアドバイザーを選ぶことが成功の鍵を握ります。M&A仲介会社やコンサルティングファームなど、実績と経験豊富な専門家に依頼することで、買い手探しや企業価値評価、交渉サポートなどを一貫して行うことが可能です。
また、アドバイザー選びでは、手数料体系や得意分野、担当者との相性などを総合的に比較検討し、自社に最適なパートナーを見つけるようにしましょう。
交渉力を高める情報収集
M&Aの交渉では、いかに自社の強みをアピールできるかがポイントになります。そのためには、精緻な経営データや市場動向の把握、競合他社の状況に関する情報収集が欠かせません。
特に売り手企業は、将来のキャッシュフローや事業の成長余地を具体的に示すことで、企業価値を高く評価してもらいやすくなります。買い手企業側としても、的確な情報をもとにデューデリジェンスを行うことで、リスクを最小限に抑えた上での買収判断が可能です。
従業員・ステークホルダーへの配慮
M&Aでは、新体制への移行に伴って社内外の混乱が生じることがあります。特に従業員にとっては、経営者の交代や組織変更は大きなストレスになり得ますので、コミュニケーションを丁寧に行い、不安を払拭することが大切です。
また、取引先や顧客、金融機関などのステークホルダーにも、適切なタイミングと方法で経緯を説明し、良好な関係を維持しましょう。信頼関係が崩れると、M&A後の事業運営に支障をきたすリスクがあります。
文化統合と組織マネジメント
M&A後の統合プロセス(PMI)では、特に企業文化や組織風土の違いにより問題が発生しやすいです。働き方や経営理念にズレがあると、社員のモチベーション低下や離職につながる可能性があります。
そこで、事前に両社の文化や価値観をすり合わせ、必要に応じて組織体制や人事制度を再構築することが肝要です。特にリーダー層が積極的にコミュニケーションを図り、相互理解と信頼関係を築くことで、成功するM&Aへとつなげやすくなります。
M&Aを成功させるためには、計画的かつ慎重なアプローチが求められます。短期的なメリットだけを追い求めるのではなく、長期的視点で統合後の姿をイメージしながら進めることが、企業のさらなる成長と安定をもたらす大きなポイントです。
M&Aにおける注意点とリスク
M&Aは多大なメリットをもたらす可能性を秘めている一方で、さまざまなリスクも存在します。企業同士が統合するという大きな意思決定には、法務や財務面をはじめ、組織文化やステークホルダーへの配慮など、細心の注意を払う必要があります。ここでは、M&Aにおける代表的な注意点とリスクを整理しました。
契約交渉時の注意点(表明保証・機密保持など)
1. 表明保証条項
M&A契約では「表明保証」と呼ばれる条項が設けられ、売り手企業が提示した情報が正確であることを保証する責任を負います。この条項に違反があれば損害賠償などの請求を受けるリスクがあるため、売り手側は適切な情報開示を徹底することが重要です。
2. 機密保持
M&Aの過程では、両社の機密情報が多く共有されます。NDA(秘密保持契約)や情報管理体制を整え、機密情報が漏えいしないよう十分に注意しましょう。また、漏えいリスクを回避するためにも、情報開示のタイミングや範囲を慎重に検討する必要があります。
買い手企業の選定リスク
M&Aを成功させるには、どの企業に売却するかが極めて重要です。買い手企業の財務状況や経営方針、企業文化などが自社と合わない場合、交渉段階で行き詰まるか、PMIの段階で統合がうまく進まない可能性があります。
また、買い手が十分な資金力を持っていないと、支払い条件が思わしくなかったり、M&A後の事業運営に影響が出るケースも考えられます。信頼できるアドバイザーの助言をもとに、複数の候補を比較検討することが望ましいです。
企業価値と価格交渉の難しさ
企業の正確な価値を算定することは、実際には難しいものです。将来のキャッシュフローや市場環境、経営陣の手腕など、定量的・定性的な要素が複雑に絡み合います。バリュエーションの結果に開きがあると、買い手と売り手の意見が対立しやすく、交渉が難航する原因となります。
売り手は情報開示を徹底し、買い手が納得できる企業の強みや将来性をアピールすることが大切です。一方、買い手もリスクを見極めながら、適切な価格で交渉を進める必要があります。
PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)における課題
M&Aは契約締結がゴールではなく、その後のPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)が大きな勝負となります。企業文化や業務プロセスの統合がスムーズに進まないと、期待していたシナジーを十分に発揮できず、むしろ混乱やコスト増を引き起こす可能性があります。
特に、中小企業においては人的リソースや管理体制が限られているため、計画的な組織づくりが求められます。買い手側は、従業員の不安を解消しながら、適切に業務を統合していくマネジメント力が必要です。
M&Aに潜むリスクをしっかりと把握し、事前の対策や適切なスキームづくりを行うことが、成功を引き寄せる鍵となります。一度のミスが企業存続に大きく影響する可能性があるからこそ、専門家やアドバイザーのサポートを活用しながら、慎重に取り組むことが重要です。
売却後の経営・組織統合の進め方
M&Aが成立した後は、実際の経営・組織統合を円滑に進めることが大きな課題となります。PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の出来具合が、M&Aの成否を左右するといっても過言ではありません。ここでは、売却後の経営体制を構築し、統合をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。
PMIとは何か
PMI(Post-Merger Integration)とは、企業買収や合併後の統合プロセスを指す言葉です。具体的には、組織や人材、業務プロセスを一体化し、新たな経営体制でシナジー効果を最大化するための取り組みを指します。
M&A直後は、旧組織の慣習や経営方針の違いによって混乱が生じることが少なくありません。計画的なPMIを実施することで、こうした混乱を最小限に抑え、新体制へソフトランディングさせることが重要です。
組織・人事制度の統合
売却後は、経営者が変わるだけでなく、組織構造や人事制度にも再編が必要になる場合があります。従業員が混乱しないよう、誰がどのポジションを担うのか、評価・報酬制度はどうなるのかなど、具体的な方針を提示することが大切です。
また、統合に伴いジョブローテーションや研修を実施すると、社員同士の理解やスキルアップにつながり、新たな組織文化の醸成をスピーディーに進めることができます。
企業文化や理念の共有方法
M&Aによって経営理念や企業文化が異なる組織が一緒になると、しばしば摩擦が起こります。文化の違いを否定するのではなく、互いの良さを理解し合い、新たな共通価値観を創り出すことがポイントです。
例えば、定期的なワークショップや経営トップからのメッセージ発信を通じて、新しい理念・ビジョンを周知徹底することが有効です。両社が尊重し合い、一体感を育む姿勢を持つことで、統合後のモチベーション向上につながります。
経営者交代時のスムーズな引き継ぎポイント
M&Aによって現経営者が退任し、新たな経営者に交代するケースでは、トップ同士の引き継ぎが企業の安定に大きな影響を与えます。以下の点を意識すると、スムーズな交代が可能になります。
1. 業務フローの可視化:重要な意思決定プロセスや社内ルール、キーパーソンなどを明確に記録・共有する。
2. 対外関係の引き継ぎ:取引先や金融機関など、主要ステークホルダーとの関係性を円滑に維持できるよう、直接の挨拶や説明を行う。
3. 社員への周知とサポート:交代の経緯や新経営者のビジョンを伝え、不安を解消しながら協力体制を整える。
このように、売却後の経営と組織統合を成功へ導くには、マネジメント力と適切なコミュニケーションが不可欠です。事前に十分なシミュレーションを行い、新体制での理念や方向性を明確に示すことで、M&Aの本質的な価値を最大限に引き出すことができるでしょう。
まとめ
会社売却は、後継者不足の解消や経営リスクの軽減など、多くのメリットをもたらす一方で、M&Aの流れやリスク管理を理解し、入念な準備を行うことが欠かせません。事業承継を円滑に進め、企業価値を最大化するためには、早期の情報収集や専門家との連携が重要な鍵となります。
特にオーナー社長の方々は、「いつかは事業を譲る」という視点を早めに持ち、経営計画や組織体制、財務状況の整備などを念入りに進めておくことで、ベストなタイミングでの売却やM&Aが実現しやすくなります。また、買い手企業との相性やシナジー効果も大きなポイントとなるため、売却後の経営や社員の雇用などにも配慮した判断が求められます。
当社、株式会社VentureForwardでは、M&Aや事業承継に関する無料相談を承っております。「いつかは事業を譲ろうと考えているが、何から始めればいいか分からない」、「企業価値を上げるために具体的にどんな準備が必要なのか」など、不安や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。専門家が丁寧にサポートし、貴社にとって最適な選択をともに模索させていただきます。
事業承継が円滑に進めば、オーナー個人の負担軽減はもちろんのこと、従業員や取引先を含む多くのステークホルダーにメリットをもたらすことができます。経営者としての責任を果たし、企業の将来に最善の道を選ぶためにも、今一度M&Aの可能性を検討されてはいかがでしょうか。