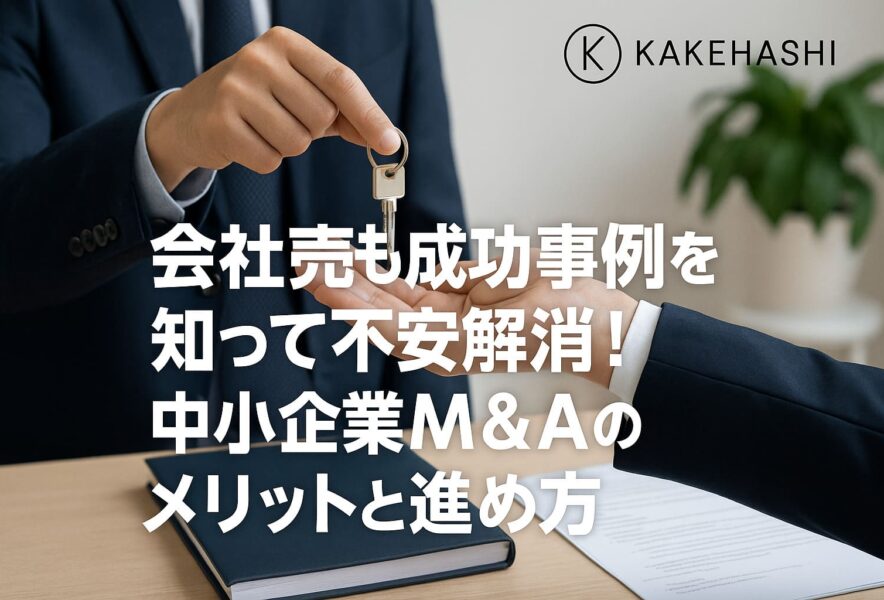「会社の将来をどうすべきか…」「自分が引退した後、この事業をどう残すべきか…」と悩む中小企業の経営者や個人事業主の方は少なくありません。
特に、後継者がいない、あるいは将来の業界環境に不安があるといった状況では、会社や事業の“出口戦略”を真剣に考える必要があります。
そんな中、近年注目を集めているのがM&Aによる会社売却です。以前は「会社を売る」というと一部の大企業の話と思われがちでしたが、今では中小企業や個人事業でも実際に売却が成立するケースが増えてきました。
実際に会社売却を通じて事業承継や再出発を成功させた事例は数多く存在します。
「社員を守りたい」「自分の人生を次のステージに進めたい」――そんな想いを叶えた経営者たちの決断には、共通点があります。
本記事では、実際の会社売却の成功事例を紹介しながら、そこから学べるポイントをわかりやすく解説していきます。
売却にあたってのメリット・デメリットや注意点、どのような会社が売却に向いているのかといった情報も併せてご紹介します。
M&Aを通じて、経営者として最善の選択をしたい方にとって、きっと参考になるはずです。
成功事例①:老舗製造業が後継者問題をM&Aで解決
創業50年を超える地方の老舗製造業A社。高い技術力と地元での信頼を武器に、安定した黒字経営を続けていました。しかし、経営者の高齢化と後継者不在という大きな課題を抱えており、事業承継の道を模索する中で、M&Aによる会社売却を決断しました。
A社の社長は、「長年一緒に働いてきた従業員の雇用を守りたい」「会社の技術を次の世代につなぎたい」という強い想いを持っていました。単なる高値売却ではなく、会社を大切にしてくれる買い手を探すことを最優先に、M&Aの専門家に相談を開始します。
その結果、同業界で事業拡大を目指していた企業がA社の技術力と地域ネットワークに着目。買い手企業は、従業員の雇用や社風の維持に理解があり、事業の継続性を重視する方針であったため、交渉もスムーズに進みました。
最終的に、株式譲渡によるM&Aが成立。経営者は安心して引退し、従業員は新体制のもとで雇用と業務を継続。A社は買収企業の資本力と営業力を活かし、以前にも増して業績を伸ばしています。
この成功のポイントは、早めの相談と、売却の目的を明確にした買い手選びにあります。「売る=終わり」ではなく、会社と社員の未来を託す選択肢としてM&Aを前向きに捉えた好例といえるでしょう。

成功事例②:IT企業が事業拡大のため会社売却を選択
都内で創業したIT企業B社は、独自開発のクラウドサービスを武器に急成長していました。従業員は10名ほどと規模は小さいながらも、リピート率の高い顧客と安定収益を確保し、将来性のある事業モデルを持っていました。
しかし、代表は次のような悩みを抱えていました。
「開発力には自信があるが、資金や営業力が足りない」
「スピード感を持って全国展開を実現するには、今の体制では限界がある」
こうした課題を打開する手段として、M&Aによる売却を検討し始めたのです。
B社は、自社の製品とシナジーがある大手IT企業数社にアプローチを開始。中でも、クラウド分野での拡大を目指していたC社が強く関心を示しました。技術力と人材の価値を高く評価し、買収後もB社の組織やブランドを活かす方針で交渉が進みました。
結果として、B社はC社のグループ会社として株式譲渡によりM&Aを実施。代表はグループ内の役員として一定期間残り、社員の待遇や働き方も改善されました。グループの販路を活かしてプロダクトの拡販が加速し、売上も順調に伸長。
この事例のように、事業を「さらに伸ばす」ためにM&Aを選択するケースも増えています。会社を売る=後ろ向きというイメージではなく、成長戦略の一環としての売却が成功の鍵となる好例です。
成功事例③:個人事業の店舗がM&Aで再生を果たす
地方都市で飲食店を営んでいたCさんは、創業から10年以上にわたり地元密着型の営業を続けてきました。味には定評があり、地元の常連客も多く抱えていましたが、コロナ禍の影響や経営者の高齢化により、業績が悪化。体力的にも厳しく、「閉店しかないかもしれない…」と悩んでいました。
そんな中、知人から「M&Aという手段がある」と紹介され、半信半疑ながらも専門家に相談を開始。店舗の立地やブランド力を評価した同業の飲食企業が、事業譲渡に興味を示しました。
Cさんの希望は明確でした。
「従業員の雇用を守りたい」「お客様にこれまで通り店を利用してもらいたい」
買い手企業はこれらの要望を尊重し、従業員の再雇用とブランドの維持を前提とした譲渡契約がまとまりました。
M&A成立後、店舗は買い手企業の支援により内装をリニューアルし、メニューの開発や広告宣伝も強化。常連客の支持を受けながら新たなスタートを切り、売上も回復傾向にあります。
Cさんは経営の一線から退き、借入金の返済を終えることができ、精神的にも大きな負担から解放されました。個人事業であっても、「売る価値」があればM&Aという選択肢は十分に有効であることを示す好例です。

会社売却のメリット・デメリット
会社売却には多くの可能性がある一方で、当然ながら注意すべき点もあります。後悔のない選択をするためには、メリットとデメリットの両方を正しく理解することが重要です。
売却による主なメリット
- 後継者問題の解決
経営者に後継者がいない場合でも、第三者に会社を譲ることで事業を継続できる手段となります。 - 創業者利益の確保
長年築いた会社の価値を売却益という形で現金化できます。引退後の生活資金や新たな挑戦資金にも活用可能です。 - 会社のさらなる成長
買い手企業の資本力やノウハウを活用することで、単独では実現できなかった事業拡大やサービス向上が期待できます。 - 経営リスクからの解放
責任やストレスが重い経営の第一線から退くことで、精神的・時間的な余裕が生まれます。 - 従業員の雇用維持
廃業と異なり、売却によって従業員の雇用や取引先との関係を維持できる可能性が高まります。
売却に伴うデメリット・注意点
- 経営権の喪失
売却後は会社の経営判断権を手放すことになります。今後の運営方針に口を出せなくなることもあります。 - 企業文化や方針の変化
買い手企業の方針によって、従来の社風や理念が変化する可能性があります。従業員や顧客への影響にも注意が必要です。 - 社内外への説明責任
売却が明るみになると、従業員や取引先から不安の声が上がることがあります。誠実な対応と情報開示が求められます。 - 交渉や契約の負担
売却価格や条件のすり合わせは簡単ではなく、専門知識や交渉力が必要になります。信頼できるアドバイザーの存在が重要です。 - 心理的な葛藤
自ら育てた会社を手放すことに対し、感情的な迷いや葛藤を抱える方も多くいます。納得感を持てるまで検討を重ねることが大切です。
会社売却は「事業の終わり」ではなく「次のステージへの選択」です。自社にとってどのような可能性があるのか、冷静に見極めることが求められます。

会社売却に向いている会社の特徴
「うちの会社は売却なんて無理だろう」と思っている方も多いかもしれません。ですが、実際には規模の大小に関係なく、売却に向いている会社の共通点がいくつかあります。ここでは、買い手企業から評価されやすい企業の特徴をご紹介します。
- 安定した収益や黒字経営が続いている
過去数年間、安定した売上と利益が出ている会社は企業価値が高く評価されやすいです。特に、売上のブレが少ない会社は信頼性が高まります。 - 独自の技術・ノウハウ・ブランドを持っている
他社にはない専門性や差別化ポイントがある会社は、買い手にとって魅力的な存在です。例としては、特許技術、長年の顧客基盤、認知度の高い商品名などが挙げられます。 - 一定の規模と人材が確保されている
従業員数や売上がある程度ある会社(たとえば従業員5~10名以上、年商数千万円以上)は、事業の自走力があり、売却後もスムーズに統合されやすいです。 - 取引先や顧客が安定している
リピーターの多い事業や、特定の業界内で確固たる顧客基盤を持つ場合は、将来の収益予測が立てやすく、買い手に安心感を与えるポイントとなります。 - 業界のトレンドや再編の流れに合致している
IT、物流、医療、介護、建設、製造業など、業界再編や集約が進む分野では、今後の成長戦略としてM&Aを活発に行う企業が増えています。こうした市場の動きに合った企業は、売却のチャンスが多い傾向です。 - オーナーが事業承継を検討している
経営者が高齢で、後継者がいない場合は、M&Aによる第三者承継が現実的な選択肢となります。早めに準備を始めれば、好条件での売却が可能です。
このような特徴がいくつか当てはまる場合、会社売却の成功可能性は十分にあります。自社の「売れるポイント」を客観的に把握することが、第一歩となるでしょう。
会社売却の進め方と成功させるための準備
会社売却を成功させるには、いきなり「売る」ことから始めるのではなく、事前の準備と戦略が重要です。ここでは、売却の流れとその過程で必要な準備について解説します。
1. 財務・法務状況の整理
まずは自社の数字を正確に把握することが出発点です。
過去3〜5年分の財務諸表や決算書、借入状況、リース契約、税務申告などを整理し、不明確な点がないよう整備しましょう。あわせて、契約書や登記情報、許認可関係の確認も必要です。
2. 自社の強みと価値の把握
買い手にとっての魅力を明確にするために、自社の強み(製品、サービス、顧客基盤、技術など)を棚卸ししましょう。必要であれば、簡易的な企業価値評価や事業価値の診断を受けることもおすすめです。
3. 希望条件の明確化
「価格が最優先」なのか、「従業員の雇用維持」や「社名の継続」が重要なのか、譲れない条件や優先順位をあらかじめ整理しておくと、交渉がスムーズになります。
4. 信頼できる専門家への相談
M&Aは専門知識と経験が必要な分野です。売却側の立場で支援してくれるアドバイザーや仲介業者に早い段階で相談することが、トラブルを避け、良い相手とマッチングするためのカギとなります。
5. 買い手企業の選定と交渉
自社に合う買い手を探す際は、単に条件の良い企業ではなく、自社の価値を理解し、理念や方向性が合う相手を選ぶことが大切です。交渉では秘密保持契約(NDA)を締結した上で、段階的に情報を開示していきます。
6. デューデリジェンス(精査)と最終契約
買い手が本格的に検討する段階では、財務・法務・労務・税務などの詳細な調査(デューデリジェンス)が行われます。この段階で不備があると取引が中止になることもあるため、事前準備が成否を分ける重要なプロセスです。
7. 従業員・取引先への説明と移行準備
成約が近づいた段階で、従業員や関係者への説明を行います。
買い手企業との合同説明会や引継ぎの計画を立て、混乱や不安を最小限に抑える配慮が必要です。
このように、会社売却には段階的な準備が求められます。思いつきではなく、「戦略的な出口」を描いて進めることが、後悔のないM&Aを実現するための第一歩です。
よくある質問(FAQ)
会社売却を検討する際、多くの経営者の方が共通して抱える疑問や不安があります。ここでは、特に質問の多い内容についてわかりやすくQ&A形式で解説します。
Q1. 小規模な会社や個人事業でも売却できますか?
はい、可能です。
近年では「スモールM&A」と呼ばれる小規模な会社や店舗、個人事業を対象とした売却も活発になっています。
店舗の立地・固定客・専門性など、事業に何らかの価値があれば売却のチャンスは十分にあります。
Q2. 赤字や業績が悪くても売却できることはありますか?
状況によっては可能です。
たとえ赤字であっても、買い手が将来性や事業との相乗効果を見込める場合は、買収が成立することもあります。
特に、人材・ノウハウ・地域性・顧客基盤などに魅力があれば、条件次第で売却は十分可能です。
Q3. 従業員や取引先に知られずに進められますか?
はい、可能です。
M&Aでは秘密保持契約(NDA)を結んだ上で進行するのが一般的です。社内外に知られることなく、最終契約まで進めることが可能です。
情報公開のタイミングは慎重に計画されるため、従業員や取引先への説明は成約直前〜直後に行うのが一般的です。
Q4. 売却までにどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には6か月~1年程度が目安です。
準備→買い手探し→交渉→デューデリジェンス→契約というプロセスを経るため、しっかりとした準備と専門家のサポートが必要です。
案件によっては3か月ほどで完了するケースもありますが、慎重に進めたい場合は半年以上を見込むとよいでしょう。
Q5. 税金はどれくらいかかるのですか?
売却で得た利益には譲渡所得税がかかります。法人と個人で課税の仕組みは異なりますが、適切な税務対策をすることで節税が可能です。
具体的な金額や節税の方法については、税理士などの専門家に事前相談することが重要です。
まとめ
会社売却は、経営者にとって人生の大きな決断です。しかし、この記事でご紹介したように、中小企業や個人事業主であってもM&Aによる成功事例は数多く存在しています。
後継者不在や経営の限界、新たなステージへの挑戦など、売却を考える理由はさまざまですが、会社や従業員の未来を真剣に考えるからこそ選ばれる選択肢です。
一方で、準備不足や情報不足のまま進めると、後悔につながる可能性もあります。大切なのは、早めに動き出し、正しい知識と信頼できるサポートを得ながら進めることです。
あなたの会社には、まだ見ぬ価値や可能性が眠っているかもしれません。「自分の会社が売れるのか?」と悩んでいる今こそが、最初の一歩を踏み出すタイミングです。
会社を手放すことは終わりではなく、あなた自身と会社の未来を切り拓く「戦略的な選択」でもあります。
無料相談のご案内
会社の将来について悩んでいる方、事業承継や売却を検討している方へ。
私たちは中小企業・個人事業主に特化したM&Aの売主専門サポートを行っています。
「会社を売るなんて自分には関係ないと思っていた」
「誰に相談すればよいのかわからない」
そんなお悩みを持つ方こそ、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
秘密厳守での対応はもちろん、専門アドバイザーがあなたの会社の現状や想いを丁寧にヒアリングし、最適な選択肢をご提案いたします。
後悔しない会社売却のために、今できることから始めてみませんか?
詳しくは下記リンクから無料相談をお申し込みいただけます。